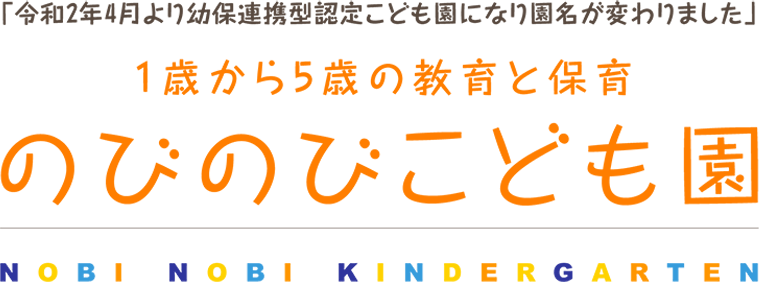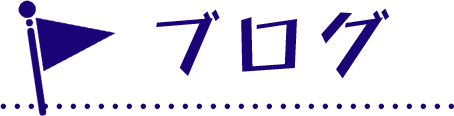2022年11月18日
秋の表情

しばらくブログの更新が止まっていたら、もう暦の上では冬になってしまいました。
せっかく撮りためた子どもたちの秋の表情をお伝えします。
上の写真は、10月19日(水)きりん組のどうぶつふれあい教室の様子です。講師はひまわり動物病院の小林先生です。小林先生は保育園に通っているお子さんがいるお父さん。5歳児さんにどうしたら伝わるのか、お仕事の写真を用意してくれたりクイズ形式にしたり色々工夫をしてくれていて、とても楽しくためになった教室でした。馬と牛は違う種類の動物なんですって!知っていました?ヒントは爪の数です。

これは運動会直後の「運動会ごっこ」の様子。

小さい組も大きい組も加わって、全員大玉転がしです。きりん組はさすがに速い。
恒例全員綱引きです。
この後、大人対子どもで対戦しました。(教頭も参加したので撮影できず)大人10人では70~80人の子どもにはとても対抗できません。勝った子どもは大喜び!
運動会の時眺めながら「やってみたいなあ」と思っていた競技ができてみんな大満足です。その他、全員リレーもありましたよ。
そして、真智子先生のお箸教室。お箸に興味をもってもらい、とにかく使ってみようというねらいの教室です。
苦戦しているひよこ組
でも、ほらつまめたよ
きりん組では数のお勉強も入ります

正しい使い方は一朝一夕では身につかないもの。おいおい給食でも教えていきますね。
そしてこれはほほえましい瞬間を撮れたのでご紹介。はとぐみのCちゃんは、運動会後きりん組さんと過ごすようになりました。玄関でCちゃんをみかけたTくんNちゃんは大喜び。「Cちゃん、こっちにおいでよ♪」
まあ行ってもいいわよ、と余裕のCちゃん。いっしょにいるとケンカも多かったんですけれど、友情もちゃんと育ってたのですね。

新しくなったウッドハウス。
これから先10年以上、のびのびの子どもたちの楽しい遊び場になって思い出に残ることでしょう。
2022年11月17日
群馬県私立幼稚園・認定こども園協会 公開保育

11月2日(水)(一社)群馬県私立幼稚園・認定こども園協会から委嘱を受け、公開保育を行いました。
これは全国で新しく始まっているESEQ方式で行われました。ESEQ方式とは今までの研究保育とは違って、自園の保育を公開し、参加者とともに自身の問いの答えを語り合って気づきを深め今後に生かしていこうという取り組みです。
当日は群馬県中から保育教諭や園長先生方が集まり、活発な意見交換が行われました。群私幼理事の方々、コーディネーターの先生、そして当日早帰り等に協力していただいた保護者の方々に感謝いたします。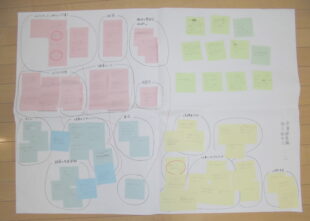
↑これは事前の打ち合わせの時作ったものですが、こんなふうに、どんどん意見を出し付箋に書き貼っていきます。張った後、分類整理し、まとめていくのです。
自分の保育の良さやのびのびこども園の特徴に気づき、明日からの保育に生かせるポイントをたくさん学ぶことができた公開保育でした。先生方もお疲れ様でした。
2022年9月28日
失敗をどうとらえるか

明後日は運動会予行です。練習も熱を帯びてきています。
年長きりん組のリレー、バトンミスがあり転んでしまう子どもがいました。競争心が強くなると、このせいで負けたと友達を責めたり必要以上に失敗を怖がったりするようになります。
しかし、担任のフォローが素晴らしかった。
とうしたら勝てるか、今までの子どもたちの話し合いの内容を振り返ります。
先生「勝つためにはどうしたらいいんだっけ?」
子ども「最後まであきらめない」
先生「Yちゃん、あきらめた?」
子ども「ううん」
先生「そうだよね、すぐ立ち上がって走ったよね。膝にけがをしても」(と傷を指さす)
「だからアンカーのAちゃんだってもう少しで追いつけそうだったよね」
A「うん、がんばって走った」
先生「Yちゃん、偉かったと思わない」
深くうなづく子ども。
バトンもどうすれば落とさないか確認します。子どもに発言させ一つひとつポイントを押さえていきます。子どもたちは次回はやってみよう、と思います。
ここまで来るのに、何度も子ども同士の話し合いの場を設けています。一対一で、グループで、全体で考えや思いを出し合いながら合意を形成していきます。もちろん子どもによって理解の仕方は様々です。でも、なんだかんだ言いながら、同じ方向に向かって納得しながら進んでいきます。
ずいぶん頑張れるようになったなあ、と思います。失敗しても失敗そのものが受容される、次があると思えることはなんと救いになることでしょう。運動会の練習を積む中で、子どもたちはこうした社会情動スキルを身に着けていっています。
まだまだドラマがありそうな運動会練習。この時期職員室にいてもそわそわして書類の仕事が手につきません(内緒)。当日をどうぞお楽しみに。
2022年9月12日
2学期に新しくなったもの②「大型遊具」
みなさんに積み立てていただいていた教材教具購入協力費で、新しい大型遊具を購入しました。その名も「WITH」。ぱんだクラブでの様子をレポートします。
以前告知しましたが、木製シャトルが古くなって取り壊すことになり、その後継として登場したチャレンジングな遊具です。購入元のジャクエツさんによると、キッズデザイン賞もとっており、群馬県での導入はのびのびこども園が初めてだということです。

幼体連の鈴木先生にお手本を見せてもらいました。ひゅう!滑り台がすごい急!
さあ、みんなでいっぺんやってみよう。

こ、こわい。むずむずする

まるで真下に落ちるような滑り台。面白い子、怖い子。またやってみたい。
WITHという名の通り、仲間と刺激を受けあってチャレンジする遊具。競ったり、真似したり、気持ちを奮い立たせられたり。学びのための要素がウィズっと詰まっています。
さあ、好きに登ってみようか。
わーい😃

登る方法は、いくつかあります。ボルダリング風に指を使ってよじ登るのだ。
ゆらゆら揺らして落ちないぞ。
?これは誰
僕でーす
ぼくもいまーす
では、今日はこれでおしまい。今度はクラスのお友達と遊んでね。
まだ、だれか先生がついていないと危険な場面があり、必ず見守りをつけようと思いますが、スリルのある動きが思いのほか子どもに好評。たくさん遊んで「筋力」「バランス力」「自分の体の感覚の理解」「挑戦するたくましさ」などの力をつけていって欲しいです。
小学生くらいまで十分楽しめます。どうぞ遊びにきてください。幼体連の小学生のスポーツ教室でも喜んで遊んでもらっています。
2022年9月12日
2学期に新しくなったもの①「厨房」

8月末に厨房工事が終了し、引き渡しになりました。現在新しい厨房で給食を作っています。「今日の給食」のページをご覧ください。↑これは、スチームコンベンションオーブンという機械の説明を受けているところです。念願の調理機器です。
スチームコンベクションオーブンとは、略して『スチコン』とも呼ばれ、熱風と蒸気を利用した自動加熱調理機のことです。一台で、「蒸す」「焼く」「煮る」「炒める」「温める」「茹でる」「揚げる」などの料理が自動的に完了します。(www.d-break.co.jp/kanetsutyouri/steam-convection/steam-convection-oven/より)

チーズトーストもあっという間に大量に焼けると栄養士の杉島さんが驚いていました。これで、オーブン料理も可能になりました。おやつやおかずにだんだんとスチコンを使った献立が増えていくことでしょう。形もかっこいい!
雰囲気もぐっと先進的になりました。自動食洗器に食器保管棚、ぴっかぴかです。
左に映っているのは、30年選手の回転釜。金子さんのおいしいカレーはこれからもこの釜で作られます。床が色分けされているのは、「洗う」「煮炊きする」「切る」「盛り付ける」などの作業場所が視覚的にわかりやすいようにです。衛生管理のため必要なことなのです。
そして…
厨房の前室ドアもサッシごと交換しました。引き戸が開けやすくなって快適!
新しく給食を作る場所。厨房は清潔な環境を保たなければならないので、みなさんどうぞ見学に来てください、とは言えないのですが、注目していただけるとありがたいです。近くをお通りの時はのぞいてください。
今後の給食に期待してください。
2022年8月4日
サマークラス②日が傾いて…第二ステージ

さて、昆虫の森でたくさんの虫に出会え色々なことを学んだきりん組のメンバー、そうめんを食べ、一休み。その後、自分の分の夕食びっくりぱん↑を作って、キャンプファイヤー係とカレー係に分かれてお仕事です。(カレー作りの様子は7月22日「今日の給食」のページに載っています)
そして自由遊び。頃は夕方日が西に傾きかけた申の刻、少し涼しく子どもたちは思い切り外を駆け回っていたのですが、担任の菜月先生と千明先生が猛獣狩りゲームを始めると、全員が集まり大盛り上がりで遊び出しました。

年長組になると、少し難しいルールのある遊びを好んで行うようになります。これは発達にかなっていて、知的な成長とともにルールがグループの共通理解となることで、より複雑なゲームになって面白いからです。まだ十分理解できない子どもも、友達の動きを見ながらルールを身に着けていきます。
「ら・い・お・ん」これは4文字の動物の名前で、4人組を作るという合図です。
「と・ら」は2人組。
「キャーっ!」集まる子どもたち。文字数が多くなるといつも遊ぶ友達だけでは足りません。誰がどこに行けば4人組ができるのか、なんだかんだ瞬時に相談して組を作ります。
この学年はマイペースさんが多く、幼い頃は個別の配慮が多く必要だったのですが、こんなにクラス全体で一つのゲームを楽しめるようになったのだと、しみじみ感動しながら様子を見ていました。
おいしくカレーをいただいて、さて、キャンプファイヤーの時間です。お泊り保育の時は7時過ぎ薄暗くなってから始めるのですが、一日だけのサマークラスです。6時に火の神様登場です。
のびのびこども園の園児の幸せを願う言葉を唱えて、引火。
赤々と燃える炎。大きさと熱を感じ目を丸くする子どもたち。
火を囲んでダンスをしましょう。大きな声で大きなフリで全身で踊ります。

炎を分けてもらって、キャンドルサービス。火をこんなにじっとみたことないなあ。心の中でお願い事をして吹き消すんだって。
そして…ここはのびのびだけの秘密の部屋。きりん組だけの内緒だよ。レポートもなし。シーッ
お部屋で閉校式をして、お家の人が迎えに来た8時にはすっかり夜になっていました。まだ疲れてないよ、お泊りだってできるよ。でももう終わりなの?寂しいなあ。

てるてる坊主が晴れにしてくれて、キャンプファイヤーができました。ふだんできない経験をたくさんして、友達との同じ思い出ができて、とても楽しかったね。
お泊り保育は、着替えや身支度・寝具の用意も自分で行い、夜を越すことで自立の足掛かりにすることがねらいです。一日だけのサマークラスでそのすべてを同じように達成させることはできませんが、親元から離れて寝る時間近くまで園で先生や友達と一緒に過ごすのは子どもたちにとってはチャレンジでしょう。
こうしてステージをクリアするたびに子どもたちは自信を深め、園でのびのび生き生き活動するようになります。サマークラスを経たきりん組が、2学期どのように活躍してくれるか楽しみです。
保護者の方は「はいチーズ」もご覧ください。このページでは載せられなかった細かい様子を写真で見ることができます。
2022年8月3日
サマークラス①「昆虫の森」が来てよって

7月22日サマークラスの日。朝はどんより、雨パラパラ。
本当は、小平の親水公園で思い切り水遊びをするはずでした。しかし、これでは川遊びは無理だということで、もう一つの計画「昆虫の森」に出かけることになりました。

スクール開校式。園長先生から楽しい一日にしようね、というお話。わくわく
見て!新しい靴買ってもらっちゃった。昆虫の森にバスで出発!

今、昆虫の森では「カブト・クワガタ展」開催中 …おや?晴れてきてるんじゃない?
そうなんです。おひさまぴかぴかいい天気。これなら親水公園にいけたんじゃない?
じつは、朝こんなふうに晴れごいをしていたんです。
窓いっぱいのてるてる坊主。よく見ると…
2cmの小さなリボンがちゃんとジャバラ折りになっている!経験が生かされています。ぜひとも晴れて欲しいとの情熱を感じますよね。
願いは通じました!しかし、昆虫の森行きになったのは…虫が大好きな今年のきりん組たち、昆虫たちが来てほしかったから朝だけ雨を降らせたんだよ。うん、きっとそうだ。
だって…

中では、今のところバッタの原っぱではみられない大人バッタやカマキリがお出迎え。カブト・クワガタを飼っている子どももたくさんいて、世界のカブト・クワガタの展示にみんな大喜び!

温室に入るとたくさんの蝶やバッタが自由に飛んでいます。すごい。あの赤い花はハイビスカス。お祭りの製作で作ったよね🌺
みてみて。教頭先生の腕にちょうちょが二羽留まってる。日焼け止めの香りに誘われたのかも。
段ボールの巨大オブジェの前でハイポーズ。
屋根の下で、凍らせたスポーツドリンクで水分補給。いいぐあいに溶けておいしかったこと。
お約束の顔出しパネルで記念写真。似合う?
楽しく、元気に園にかえって来ました。虫さんお招きありがとう。
後半につづく
保護者の方は、「はいチーズ」で全容が見られます。写真を購入しなくても大丈夫です。どうぞお訪ねください。
2022年8月3日
平均8分16秒

8分16秒とは、110番通報からパトロールカーが現場に到着するまでの平均時間です。この「リスポンスタイム」は、過去10年の年間平均が6分54秒から8分9秒であったのに比べ、令和3年1月~11月の平均は最も遅く、8分16秒だったそうです。(2022.1.10 テレ朝NEWSより)
7月12日、不審者侵入を想定した防犯訓練を行いました。年度の前半に行うこの訓練は10分間保育室で集まって静かにするということです。
10時に不審者が園内に侵入したという暗号が放送されます。保育者は打ち合わせ通り窓を閉め、出入り口を施錠し子どもを保育室の死角に集めます。一瞬で静まり返る園舎内。
低年齢児は不審者侵入の意味を理解することが難しくトラウマにもなりかねないので、絵本を見ながら時間を過ぎるのを待ちます。
ドアを開けて奥を覗かないと、子どもがいるかどうかわかりません。
10分たち、解除の暗号を放送聞いて、今行った訓練の理由や安全に過ごすためのふるまいについて学びます。子どもたちはみな真剣に話を聞いていました。
地域に開かれたこども園であることと安全な子どものための空間をどう両立していくのか、防犯マニュアルの改訂を進めています。2月には桐生警察スクールサポーターさんをお迎えして、実際に不審者が侵入したときの職員の対応を含め年度2回目の防犯訓練を行います。
2022年8月3日
7月7日七夕まつり

感染症予防のため、すべての行事を中止にしてしまうのではなく、行事で育てられるものはできるだけ子どもたちに与えようと、七夕祭りを行いました。
恒例、学年を超えたペアによるフォークダンス。

大きい組は小さい組に慕われてうれしい。小さい組はお兄さんお姉さんが優しくしてくれてうれしい。
※余談
教頭はフォークダンスというと民族舞踊が入らないとだめなんじゃないかと思い込んでいましたが、日本フォークダンス連盟の次の記述によると
『フォークダンスは、みんなで踊ることに意味があるダンスです。そのため、フォークダンスは固有のものではなく“みんな”のものであり、そして誰にでも踊れるダンスということが特徴です。踊る際に多少の個人差(年齢、性別、上手下手、経験)があったとしても、“みんな”で踊るということが大切であって、厳しい型にとらわれることがありません。大事なことは、みんなが同じ目的を持って楽しく踊ることであり、みんながその一体感を感じることhttp://www.folk-dance.or.jp/about/genre.html』
ということなので、みんなで七夕祭りを楽しむために今どきの音楽でダンスを踊るのもフォークダンスでいいのだとの結論に至りました。
学級で整列して、司会者の紹介です。大役に選ばれたきりん組の子どもたち、ドキドキです。
各学級で歌の披露。これはうさぎ組の「すうじのうた」。見てください、この表情^^
よかったよ、とお姉さんに駆け寄るRくん
上には笹飾りに思い思いのお願い事が揺れていました。かなうといいね。
残念ながら今年の七夕祭りはここまで。この後は学級に分かれて由来のお話を聞いたり、給食に出た七夕ゼリーに舌鼓をうったりしたのでした。(7月7日『今日の給食』をご覧ください^^)
来年は七夕の劇ができるといいなあ。