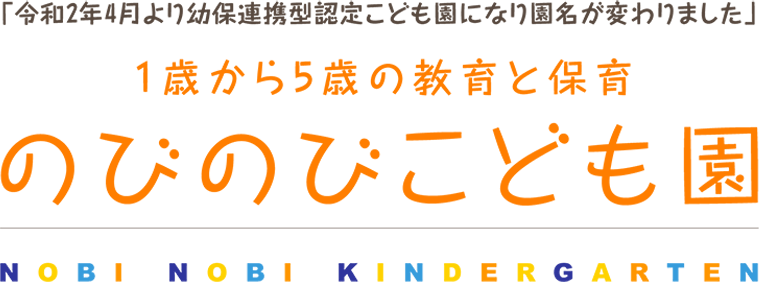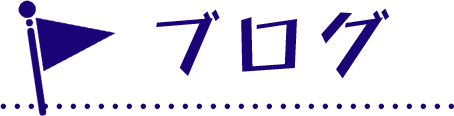2018年11月12日
幼保小中はつながっている
11月8日、新里中学校の学校公開授業を参観してきました。これは、新里町幼保小中教育保育連携会議が主催する授業公開で、教育の接続のための情報共有を目的に毎年行われているものです。小学校、幼稚園、保育園にも、各学校の先生が参観に見え、意見交換をできるようになっています。
たいへん勉強になりました。中学校に提出した感想を載せます。長文ですが、興味のある方はお読みください。(教頭記す・一部省略あり)
*************************
本日は、学校公開に参加させていただき、たいへんありがとうございました。「幼児期にはぐみたい資質・能力」が中学校につながっているのかどうかを確認したくてうかがいました。 結論からいうと、「つながっている!」と感じられました。
幼児期の学びは、長く小学校以降の学びとは別と考えられていましたが、幼児期に、子ども自ら感じ、考え、行動する機会が減って資質能力が育っていなければ、本日の理科の実験の授業で目標とされる、主体的で対話的な深い学びは成り立たないだろうと思いました。
[1年B組の理科の実験で、幼児期の学び、育った姿が生かされるだろうと思った点]
●自然現象で、「不思議!」「面白い!」と感じ、興味をもって観察し繰り返し行うこと
●協力して活動すること。できる子だけが一人でどんどん進めるのではなく、グループで役割を分担し まとめていく。
●クラスの友達を信頼し、思いや感じたことを自信をもって発言すること
●知識や経験を組み合わせ、よりよい答えを導こうとすること などなど
これらは、教師が教えてさせるだけでは育たないものです。目に見える「何かができる」姿だけにとらわれず、日々の生活、遊びの中でしっかり経験させ、育んでいきたいと思いました。
また、3年D組の国語の授業を拝見しました。文法の復習で、固くなった私の頭ではちんぷんかんぷんでしたが、先生の軽妙な授業運びで、飽きずに45分聞いていられました。さすがだな、と思ったのは、ほめ方が上手だなあということです。幼稚園でも「わかりやすくほめる」ことを心がけていますが、先生からは、中学生にあった認める言葉がどんどん出てきて、これではついつい生徒はがんばってしまうだろう、と思いました。そして、やや関心を持ちにくそうな生徒に対し、先手で声をかけ、授業に引き込んでいらっしゃいました。また、到達度が高い生徒用に補充プリントも用意されていました。新里中が落ち着いて学習できる環境が整ってきたのは、こうした先生方の努力があってこそなんだろうと敬服いたします。
単語を覚えること、文法を理解すること、地味な積み重ねが学力の向上につながりますよね。幼児期は、「楽しいからやる」が基本ですが、6歳年長児になると、見通しを持って努力を重ねることができるようになってきます。幼児期に「がんばってきたから、これができるようになった」という実感を経験できていたとしたら、強味でしょう。自ら必要を感じてできるような環境を用意して、味わわせることができたらよいなあ、小学校、中学校と生きる学びに向かう力が育つなあと思いました。
多くの学び、発見があった学校公開参観でした。ありがとうございました。幼稚園、保育園、こども園にもぜひおこしください。
2018年10月26日
鮭の味噌マヨネーズ焼き
2018年10月25日
引き渡し訓練
10月24日(水)大きな地震が起きた想定で、子どもの引き渡し訓練を行いました。お仕事の休憩時間を調整していただいたり、おじいちゃん・おばあちゃんにお願いしていただいたり、ご協力ありがとうございます。また、新里東小の学校行事と重なってしまい、保護者の方には泡立たしい思いをさせてしまいました。申し訳なかったです。
平成23年の東日本大震災から時が経ち、記憶が薄れつつありますが、全国で大きな地震は頻繁に起きています。群馬県でも、818年に弘仁地震と呼ばれる大きな地震があり、新里にも大久保断層という活断層があることが発掘調査で確認されています。大きな地震があったとき、「安全に」「確実に」「速やかに」子どもを保護者に引き渡せるか、園にとっては大切な訓練です。
駐車場には本当の地震の時は係をおけないかもしれないので、保護者にお任せして駐車していただきましたが、スムーズでした。

「引き渡し訓練」メールを受信してから園まで迎えに来るという手順なので、遠い方は少し時間がかかります。子どもを励ましながら、お迎えを待ちます。


誰が何時に迎えに来たか、知らない人であれば引き渡しカードがあったか、メール受信の確認返信があったか、いざというときに保護者と連絡がとれる体制にあるか、ポイントをチェックしていきます。
今年は、スポーツクラブの曜日と重なって、引き渡し後クラブに参加するお子さんが多く、落ち着かなくなってしまいました。本来は、家に着くまでが避難訓練。帰る時に、ここは危ないかもしれない、安全に回り道はあるだろうかなどど考えながら、お子さんとお話して帰っていただきたかったのですが、叶いませんでした。何かの機会にご家庭でしていただけるとありがたいです。来年は日程を組む時、気を付けます。
2018年10月24日
10/16動物ふれあい教室
恒例のきりん組動物ふれあい教室を行いました。講師は地元カール動物病院の長島先生です。
園で世話をしているうさぎの心音と人間の心音を比べたり、動物の質問に長島先生に答えていただいたり、楽しく有意義な時間を過ごしました。
質問1 何でトラは、黄色と黒のもようなんですか。 回答1 エサをとるために、この模様が都合がいいのです。闇の中にも溶け込んで見えなくなります。 質問2 家で飼っているひばりのパグは、どうしてかわいいのですか。 回答2 愛情をもって育てているからです。でも、動物はどれもかわいいよ。(さすが獣医さん^^) 質問3 何でぞうはりんごを食べるんですか。 回答3 ぞうはりんごが大好きなんです。でも野生ではりんごはあまりない。動物園では草の量を確保するのが難しいため、(カロリーの高い)りんごをあげています。・・・・(そうだったんだ!園の先生も知りませんでした。)
などなど。長島先生はときどきよーく考えながら、子どもらしい質問に答えてくださいました。
2018年10月22日
航空写真撮影
10月10日に飛行機からの園舎の航空撮影、10月19日(金)には併せて全園児撮影をしました。2階からひまわり空撮のフォトグラファーがカメラをかまえ、実習生さんにシャッターを押すときにお人形を跳び出させてもらって注目させ、なんとか終了。0歳児から5歳児まで全員が良いお顔で撮れることはほぼキセキ。提案にはなるべくたくさんいいお顔で撮れている写真を選んでいただくことにしました。
空撮というと、高額でとても手がでないと思っていましたが、今回近隣の学校数校と同時に行えたため、現像料のみで撮ってもらえることになりました。ラッキー!
見本となる他園の航空写真を見せたときの、きりん組の反応。「これ、どこの幼稚園?上からみるとこんなふうなんだね。」「おれんち、見えるかなあ」。自分の過ごしているところを俯瞰するというのはおそらく園児は初めての経験。感動が喚起され、知的好奇心を刺激されることでしょう。地図もイメージしやすくなりますね。数年に一度くらいは行いたいものです。
2L版なら数百円で購入できるそうです。どうぞ買っていただき、お子さんとお話しながらいろいろな発見をしてください。
2018年10月22日
運動会後の運動会遊び
10月6日(土)は暑すぎないちょうどよいお天気で、運動会が開催されました。みんな、練習通りの実力を出せ、感動の連続でした。
さて、運動会が明けて、10月11日(木)は雨。外で遊べません。しかし、運動会の共通の経験を活かし、年中うさぎ組と年長きりん組で、大いに遊びが盛り上がったので紹介します。
雨が降っていたので、S君が運動会の遊戯で踊ったU.S.A.を室内で踊りたくなり、音楽をかけてくれるように先生に頼みました。きりん組担任の千明先生は、U.S.A.がかかるとうさぎ組が遠くから観ながら踊っていたと担任岩瀬先生に聞いていたので、「うさぎ組さんを誘ってみたら」と提案。今までは、入りたくても入れなかったきりん組の部屋に呼ばれて、うさぎ組は大喜び。(実際は入っていいのですが、子どもなりに空気を読み、入り口に行ってはちょっとアピールして逃げての繰り返しをしていました。)S君の後に続いて、ほとんどの子どもたちがきりん組の保育室に入っていきました。


先生はきりん組。うさぎは見て真似て踊ります。さて、組体操もしたいとの声があがり、跳び箱、数人ずつ組んで作る形も音楽に合わせて行いました。ここは合図で順番に出ていくんだよ、ときりんティーチャー立派です。保育者は危なくないように見守りながら、合図を出しました。



この遊びは楽しかったようで、翌12日も続きました。ところどころ混ざる人や、みんなが踊る音楽を聴きながら鼻歌交じりに好きな遊びをする人もいて、みんなで運動会の余韻を楽しみました。
楽しそう、すごいと憧れの眼で見ていた年長きりん組の遊戯・演技を、教えてもらってできて念願叶った年中うさぎ組。たくさん楽しんで、一生懸命練習して、高い目標に向かってやってきたことを、年下の園児に教えてあらためて自分のやりとげたことを振り返った年長きりん組。なんて嬉しい時間だったことでしょう。
2018年10月18日
2歳児の写生会
10月18日(水)は、幼稚園の写生会でした。
写生は「景色や事物のありさまを見たままに写し取ること」で、「観察画」であります。のびのび幼稚園は長年「芸術の秋」である10月に写生会を行っています。
今年、にじ組の担任の久保田先生から相談を受けました。2歳児は、やっと円を描くことができるようになってきた時期。子どもたちの描く力に合わせて、りんごを描きたいと。
3歳以上児は、園で飼っているうさぎ、にわとり、ミニチュアホースを描きます。2歳児以下に観察画は難しいということで、昨年まではうさぎに親しんだ後、先生が描いたうさぎ型の枠にタンポでぽんぽんと色を付け、ふわふわした感じを出して完成、としていました。
2歳児は、錯画期から象徴期に移る時期。手と目を使って偶然に出来上がった形に意味をつけていく時期で、見て形を描かせるのには無理があります。子どもの描けるマルをりんごに見立てて、色や模様に気づかせていくというのはとてもいいということで、さっそく取り組んでみました。
色をよく見たら、ただの赤じゃなくて、黄色もあることに気づき、思い思いのところに黄色を塗りました。そして、てんてんがあったので、てんてんてんと描きました。思い通りのありのままが描けたので、2歳児にじ組大満足です。これぞ、2歳児の写生会でした。 
 おやつにそのりんごをむいてもらい、みんな笑顔で食べていましたよ。
おやつにそのりんごをむいてもらい、みんな笑顔で食べていましたよ。