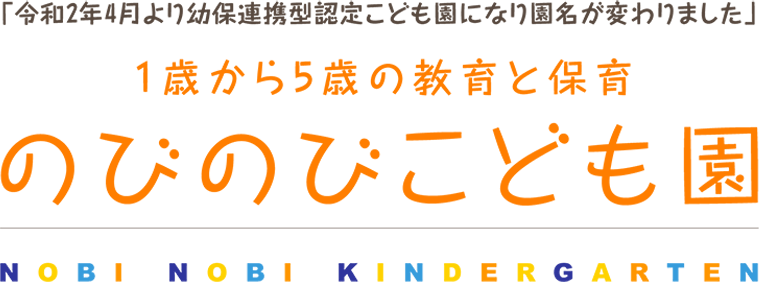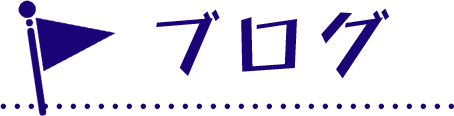2022年9月12日
2学期に新しくなったもの①「厨房」

8月末に厨房工事が終了し、引き渡しになりました。現在新しい厨房で給食を作っています。「今日の給食」のページをご覧ください。↑これは、スチームコンベンションオーブンという機械の説明を受けているところです。念願の調理機器です。
スチームコンベクションオーブンとは、略して『スチコン』とも呼ばれ、熱風と蒸気を利用した自動加熱調理機のことです。一台で、「蒸す」「焼く」「煮る」「炒める」「温める」「茹でる」「揚げる」などの料理が自動的に完了します。(www.d-break.co.jp/kanetsutyouri/steam-convection/steam-convection-oven/より)

チーズトーストもあっという間に大量に焼けると栄養士の杉島さんが驚いていました。これで、オーブン料理も可能になりました。おやつやおかずにだんだんとスチコンを使った献立が増えていくことでしょう。形もかっこいい!
雰囲気もぐっと先進的になりました。自動食洗器に食器保管棚、ぴっかぴかです。
左に映っているのは、30年選手の回転釜。金子さんのおいしいカレーはこれからもこの釜で作られます。床が色分けされているのは、「洗う」「煮炊きする」「切る」「盛り付ける」などの作業場所が視覚的にわかりやすいようにです。衛生管理のため必要なことなのです。
そして…
厨房の前室ドアもサッシごと交換しました。引き戸が開けやすくなって快適!
新しく給食を作る場所。厨房は清潔な環境を保たなければならないので、みなさんどうぞ見学に来てください、とは言えないのですが、注目していただけるとありがたいです。近くをお通りの時はのぞいてください。
今後の給食に期待してください。
2022年8月4日
サマークラス②日が傾いて…第二ステージ

さて、昆虫の森でたくさんの虫に出会え色々なことを学んだきりん組のメンバー、そうめんを食べ、一休み。その後、自分の分の夕食びっくりぱん↑を作って、キャンプファイヤー係とカレー係に分かれてお仕事です。(カレー作りの様子は7月22日「今日の給食」のページに載っています)
そして自由遊び。頃は夕方日が西に傾きかけた申の刻、少し涼しく子どもたちは思い切り外を駆け回っていたのですが、担任の菜月先生と千明先生が猛獣狩りゲームを始めると、全員が集まり大盛り上がりで遊び出しました。

年長組になると、少し難しいルールのある遊びを好んで行うようになります。これは発達にかなっていて、知的な成長とともにルールがグループの共通理解となることで、より複雑なゲームになって面白いからです。まだ十分理解できない子どもも、友達の動きを見ながらルールを身に着けていきます。
「ら・い・お・ん」これは4文字の動物の名前で、4人組を作るという合図です。
「と・ら」は2人組。
「キャーっ!」集まる子どもたち。文字数が多くなるといつも遊ぶ友達だけでは足りません。誰がどこに行けば4人組ができるのか、なんだかんだ瞬時に相談して組を作ります。
この学年はマイペースさんが多く、幼い頃は個別の配慮が多く必要だったのですが、こんなにクラス全体で一つのゲームを楽しめるようになったのだと、しみじみ感動しながら様子を見ていました。
おいしくカレーをいただいて、さて、キャンプファイヤーの時間です。お泊り保育の時は7時過ぎ薄暗くなってから始めるのですが、一日だけのサマークラスです。6時に火の神様登場です。
のびのびこども園の園児の幸せを願う言葉を唱えて、引火。
赤々と燃える炎。大きさと熱を感じ目を丸くする子どもたち。
火を囲んでダンスをしましょう。大きな声で大きなフリで全身で踊ります。

炎を分けてもらって、キャンドルサービス。火をこんなにじっとみたことないなあ。心の中でお願い事をして吹き消すんだって。
そして…ここはのびのびだけの秘密の部屋。きりん組だけの内緒だよ。レポートもなし。シーッ
お部屋で閉校式をして、お家の人が迎えに来た8時にはすっかり夜になっていました。まだ疲れてないよ、お泊りだってできるよ。でももう終わりなの?寂しいなあ。

てるてる坊主が晴れにしてくれて、キャンプファイヤーができました。ふだんできない経験をたくさんして、友達との同じ思い出ができて、とても楽しかったね。
お泊り保育は、着替えや身支度・寝具の用意も自分で行い、夜を越すことで自立の足掛かりにすることがねらいです。一日だけのサマークラスでそのすべてを同じように達成させることはできませんが、親元から離れて寝る時間近くまで園で先生や友達と一緒に過ごすのは子どもたちにとってはチャレンジでしょう。
こうしてステージをクリアするたびに子どもたちは自信を深め、園でのびのび生き生き活動するようになります。サマークラスを経たきりん組が、2学期どのように活躍してくれるか楽しみです。
保護者の方は「はいチーズ」もご覧ください。このページでは載せられなかった細かい様子を写真で見ることができます。
2022年8月3日
サマークラス①「昆虫の森」が来てよって

7月22日サマークラスの日。朝はどんより、雨パラパラ。
本当は、小平の親水公園で思い切り水遊びをするはずでした。しかし、これでは川遊びは無理だということで、もう一つの計画「昆虫の森」に出かけることになりました。

スクール開校式。園長先生から楽しい一日にしようね、というお話。わくわく
見て!新しい靴買ってもらっちゃった。昆虫の森にバスで出発!

今、昆虫の森では「カブト・クワガタ展」開催中 …おや?晴れてきてるんじゃない?
そうなんです。おひさまぴかぴかいい天気。これなら親水公園にいけたんじゃない?
じつは、朝こんなふうに晴れごいをしていたんです。
窓いっぱいのてるてる坊主。よく見ると…
2cmの小さなリボンがちゃんとジャバラ折りになっている!経験が生かされています。ぜひとも晴れて欲しいとの情熱を感じますよね。
願いは通じました!しかし、昆虫の森行きになったのは…虫が大好きな今年のきりん組たち、昆虫たちが来てほしかったから朝だけ雨を降らせたんだよ。うん、きっとそうだ。
だって…

中では、今のところバッタの原っぱではみられない大人バッタやカマキリがお出迎え。カブト・クワガタを飼っている子どももたくさんいて、世界のカブト・クワガタの展示にみんな大喜び!

温室に入るとたくさんの蝶やバッタが自由に飛んでいます。すごい。あの赤い花はハイビスカス。お祭りの製作で作ったよね🌺
みてみて。教頭先生の腕にちょうちょが二羽留まってる。日焼け止めの香りに誘われたのかも。
段ボールの巨大オブジェの前でハイポーズ。
屋根の下で、凍らせたスポーツドリンクで水分補給。いいぐあいに溶けておいしかったこと。
お約束の顔出しパネルで記念写真。似合う?
楽しく、元気に園にかえって来ました。虫さんお招きありがとう。
後半につづく
保護者の方は、「はいチーズ」で全容が見られます。写真を購入しなくても大丈夫です。どうぞお訪ねください。
2022年8月3日
平均8分16秒

8分16秒とは、110番通報からパトロールカーが現場に到着するまでの平均時間です。この「リスポンスタイム」は、過去10年の年間平均が6分54秒から8分9秒であったのに比べ、令和3年1月~11月の平均は最も遅く、8分16秒だったそうです。(2022.1.10 テレ朝NEWSより)
7月12日、不審者侵入を想定した防犯訓練を行いました。年度の前半に行うこの訓練は10分間保育室で集まって静かにするということです。
10時に不審者が園内に侵入したという暗号が放送されます。保育者は打ち合わせ通り窓を閉め、出入り口を施錠し子どもを保育室の死角に集めます。一瞬で静まり返る園舎内。
低年齢児は不審者侵入の意味を理解することが難しくトラウマにもなりかねないので、絵本を見ながら時間を過ぎるのを待ちます。
ドアを開けて奥を覗かないと、子どもがいるかどうかわかりません。
10分たち、解除の暗号を放送聞いて、今行った訓練の理由や安全に過ごすためのふるまいについて学びます。子どもたちはみな真剣に話を聞いていました。
地域に開かれたこども園であることと安全な子どものための空間をどう両立していくのか、防犯マニュアルの改訂を進めています。2月には桐生警察スクールサポーターさんをお迎えして、実際に不審者が侵入したときの職員の対応を含め年度2回目の防犯訓練を行います。
2022年8月3日
7月7日七夕まつり

感染症予防のため、すべての行事を中止にしてしまうのではなく、行事で育てられるものはできるだけ子どもたちに与えようと、七夕祭りを行いました。
恒例、学年を超えたペアによるフォークダンス。

大きい組は小さい組に慕われてうれしい。小さい組はお兄さんお姉さんが優しくしてくれてうれしい。
※余談
教頭はフォークダンスというと民族舞踊が入らないとだめなんじゃないかと思い込んでいましたが、日本フォークダンス連盟の次の記述によると
『フォークダンスは、みんなで踊ることに意味があるダンスです。そのため、フォークダンスは固有のものではなく“みんな”のものであり、そして誰にでも踊れるダンスということが特徴です。踊る際に多少の個人差(年齢、性別、上手下手、経験)があったとしても、“みんな”で踊るということが大切であって、厳しい型にとらわれることがありません。大事なことは、みんなが同じ目的を持って楽しく踊ることであり、みんながその一体感を感じることhttp://www.folk-dance.or.jp/about/genre.html』
ということなので、みんなで七夕祭りを楽しむために今どきの音楽でダンスを踊るのもフォークダンスでいいのだとの結論に至りました。
学級で整列して、司会者の紹介です。大役に選ばれたきりん組の子どもたち、ドキドキです。
各学級で歌の披露。これはうさぎ組の「すうじのうた」。見てください、この表情^^
よかったよ、とお姉さんに駆け寄るRくん
上には笹飾りに思い思いのお願い事が揺れていました。かなうといいね。
残念ながら今年の七夕祭りはここまで。この後は学級に分かれて由来のお話を聞いたり、給食に出た七夕ゼリーに舌鼓をうったりしたのでした。(7月7日『今日の給食』をご覧ください^^)
来年は七夕の劇ができるといいなあ。
2022年7月6日
バッタの原っぱが来年も続きますように

夏が来ました!
園の西、通称バッタの原っぱでは夢中で虫探しをする子どもが大勢います。
「いたぞ!」「どこどこ?!」
今年は梅雨明けが早く、赤ちゃんバッタがたーくさん生まれています。
しかし、毎年問題となるのが、乱獲。何十匹捕まえても飼い切れず死なせてしまうことも…。その場で言葉で説明してもなかなか伝わらず、言われて逃がすだけではせっかくの学びの機会を失ってしまう。そこでその日のお昼過ぎ、きりん組で「うまれたよ!バッタ」を読みました。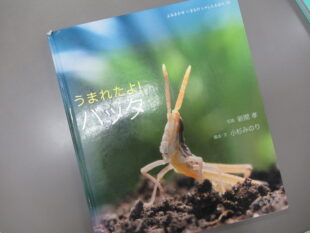
岩最書店「よみきかせいきものしゃしんえほん・16」
バッタの一生。おもしろくてかわいいバッタ。でも生まれて死ぬまでがあるよ。ごはん(はっぱ)を朝から晩までばりばり食べるよ。脱皮をしながら大きくなるよ。子どものバッタは羽が無いか小さいよ。
そして、大人になる前に死なせてしまうと卵が産まれない。卵が産まれないとバッタの原っぱにバッタがいなくなってしまう。ではどうしたらいい…
一つひとつ子どもと対話しながら読み進めます。子どもたちは考えます。
そうか、おもしろいからといって全部捕っちゃだめなんだ。
さて、次の日バッタ探しは続きます。しかし、見方が少し変わりました。
「あっ、脱皮した抜け殻!」
「羽が小さいから、まだ子供のバッタなんだね。」「きりん組くらいかな?」
「ぼく、2匹だけ大切に育てることにするよ。」
捕るより、観察することに重点が移りました。そして虫探しは明日も続くでしょう。
先日SDSsについての講習会に参加したのですが、SDSsの思想は多岐にわたり全体像を理解するのはとても難しいと感じました。しかし、基礎になることが幼児の生活にありました。おもしろいからといって好きなだけ手に入れてしまうと、その枠組みや前提そのものを壊してしまうことになるかもしれない。それが繰り返されると持続可能な社会は実現されないでしょう。その実感を得るのは、こうした自然の中での小動物とのかかわりはいいなあ、などと思った暑い日でした。(教頭・須田)
2022年7月4日
今年はプール、当たり年かも

記録上一番早い梅雨明けとか!
毎年園のプールは1学期中10回も入れないんです。プール開きは6月頭ですが、天気がよくても気温が低ければ入れないし梅雨が明けるのは7月半ばですし…。
こんなに早く夏がきたということは、もしかして今年はプールの当たり年かも⁉
あまり暑くても熱中症の危険があるので注意が必要ですが、体調を整えて、水分をしっかりとって、やっぱり夏はプールでしょということで各クラスの表情をお知らせします。

たまご組は、保育室の前にテントを張って日陰を作り水遊びです。
水に触っているだけで気持ちいいね。先生にやさしく水をかけてもらってだんだんと水に慣れていきます。
にじ・おひさま組はもう少しダイナミックにホースで水をびゅーっ!園庭でも遊んだからもう怖くないよ。
ペットボトルのシャワー、おもしろい。おむつがとれると大きいプールに入れますよ。今年の夏でとれるといいね。
ひよこ組はまだ水は少ないのですが、この通りたっぷり楽しんでいますよ。先生に向かって、水鉄砲エイ!
頭までびっちょり。でも冷たくないよ、すごく気持ちいい。
うさぎ組。さあ、プールサイドに突入だ!
流れるプールだぞ、いっちに、いっちに!水をふむぞ、けりあげるぞ!うわーい
さて、園じゅうに響き渡る歓声を上げてエネルギー弾ける遊び方をするきりん組。合図で二組に分かれて水をかけあいます。
水の高さもけっこうありますが、水の中で怖がる子はいません。
ひと遊びした後、手作りの浮き具が出され、「みんなで相談して使ってみてね」とだけ先生は告げて、遊び再開。どうなるかな…とみていると
ちゃんと「貸して」と言って順番に使えていました。さすが年長きりん組。使いたいのに言い出せない子はちゃんと先生が見ていて、「ほら、今行ってみたら?」とフォローしていました。これも学び。
さあ、暑さよ来い。夏を楽しむぞ
子どもは水の子です^^
2022年5月24日
晴天☀さつまいもの苗植え

5月24日(火)晴天。さつまいもの苗植えをしました。
3歳児以上ははだしで行きます。朝、先生たちが危ないものがないか点検し畑に続く天神様境内の西の道をきれいに掃きました。冷たくていい気持ち。
にじ組さん、植え方の説明を聞きます。よく見ています。こうやって畝のベッドに寝かせて土のお布団をかけるんだって。
ひよこ組は初めての子もいます。これが畑というものなのか。
やさしくやさしく寝かせてあげよう。おいしいさつまいもがなりますように。
はと組さんも上手に植えることができました。畑に足をおろすの怖くないよ、大丈夫だよ。やってみる?
うさぎ組。ちょっと待ってて、みんなに苗が配られてから植えるんだって。あ、そうか。
たまご組は土の感触を楽しみ、初夏の自然を感じるのがねらい。ほら、苗をもってごらん
きりん組は慣れたもの。これがおいしいさつまいもになることを知って見通しをもって植えています。
焼き芋が好きな方、スイートポテトが好きな方、これがさつまいもの元だって知っていました?

今日はのびのび広場の日。体験できた人も嬉しそう。
運動会が終わったころ、さつまいも掘り。成長を観察しながら楽しみに待ちましょう。
おまけ①畑で見た花
正解は次回。


そして「今日の給食」でも紹介されたいちご。今日もたくさんなっていました。ひよこ組がいちご狩りをして帰りましたよ。
おまけ②苗植えのあとに


なんと年長きりん組は組体操の練習。そして、園庭で先生がホースで水を撒く中はだしでしばらく鬼ごっこを楽しんでいました。子どものエネルギーってすごい!
2022年5月20日
保育参観日和

5月18日、19日は保育参観でした。
屋内ですとどうしても密になってしまうので、園庭で一家庭一人参観として、お家の方にお子さんの様子を見に来ていただきました。両日とも天気がよく、気持ちのよい参観日になりました。
18日は、2歳児にじ組と0・1歳児たまご組の参観日でした。上の写真は、にじ組のお引越しゲームの様子です。「引っ越しどーこだ!」の合図で、アンパンマンのキャラクターの絵の上に移動します。当日はお父さんの参加率が高く、少し照れながらも一緒に遊んでくれました。
「大きいからうまく描けているかわからなくて…」と先生たち。大丈夫、とても上手ですよ。

こちらは、たまご組のお散歩の様子。
0・1歳児さんは、大好きなお家の方がいるとそばにいたくて、園でのいつもの様子を見ていただくことができません。それなので、一緒にいつもの散歩コースを歩いていただき、どんなことをしているのか同じ体験をしていただきました。保育参加ですね。
ジャックにご飯をあげているんだよ。
これは19日の3歳児ひよこ組。ブランコは最初にルールを覚えるのが肝心。安全な距離をとって並んで順番に乗ります。いーち、にーい、さーん…じゅう!かーして
代われたらお家の人にハイポーズで写真をとってもらいます。ずーっとこの瞬間を楽しみにしていたの。やった!かっこよく決まった。
4歳児うさぎ組は、綱とりゲームです。一日園長先生(※お知らせをご覧ください)に合図を出してもらって自分の陣地に綱(縄跳び)を引っ張っていきます。たくさんの綱を集めたチームの勝ち。
最後は力勝負になります。はと組の4歳児さんも参加しています。さあ、味方が苦戦しているぞ、助けにいこう!負けると泣いて怒る子どももいます。勝つために頑張るけれど、負けることもある。気持ちを切り替えて次に向かおう。それも学びです。
きりん組はへびじゃんけんです。じゃんけんの勝ち負けがぱっとわかり、ラインに沿って走ることができてとやはり年長児らしいゲームです。スターターのリーダーが「絶対勝つぞ!」と気勢をあげます。「おー」っと答えるメンバーたち。
どーん、ジャンケンポン!味方が負けたら、次の人が自陣を飛び出します。早く早く!急がないと負けちゃう。なんて楽しいんでしょう。はと組のCちゃんも上手に参加できました。
昨年は雨で中止にした行事です。今年は少しでも見に来れられてよかったと保護者からのお声をいただきました。家族代表でおじいちゃまが参観にこられたお家もありました。子どもがすくすく育っている様子、多くの方に見守っていただきたいです。これから機会が増えますように。
2022年4月28日
今が旬です いちご狩り

2年続けて中止にしていたいちご狩り。桐生タイムスでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、新里の南 中村いちご園は、毎年桐生市内の子どもの施設を招待して、無料でいちご狩りを開放しています。太っ腹!今年は参加を申し込ませていただきました(^^)V

ビニールハウスに着くと、満開のパンジーがお出迎え。社長の中村さんにご挨拶していざ入場。
みずみずしく実る旬のいちご。中村いちご園のいちごは、予約しないと買えない人気の品。これがいちご狩りでいただけるなんて、とてもありがたいことなんです。
こんなふうになっているんだね。ハチさんはお仕事しているから見つけたらそっとしておいてね、と中村さん。白い花がまだまだついていて、これからも実がなりそうです。
とっていいよ。うーん、おいしそう。おいしい!
ぼく、とても楽しみにしていたんだよ。
少し移動してみようか。今日は歩き食べもOKよ。
見て!こんなに大きい
白いのも試していいんだって。
うん、いちごの味♡ けっこうおいしい
お土産も採りました。弟が喜ぶな。
ありがとうございました。来られてよかったです。
貴重な直接体験。少しずつ、以前に経験できたことがもどってきています。